「歯はちゃんと磨いてるはずなのに、なんだか口が臭う…」
そんな悩みを抱えている人は意外と多く、その原因のひとつに“親知らず”が関係している場合があります。
本記事では、親知らずが口臭にどう影響するのか、放置することで起こり得るリスク、そして具体的な対策法について解説します。
目次
親知らずってどんな歯?
親知らずは「第三大臼歯(だいきゅうし)」とも呼ばれ、10代後半から20代前半にかけて奥歯のさらに奥に生えてくる歯です。
まっすぐ正常に生える人もいれば、横向き・斜め向きに生えたり、歯ぐきの中に埋まったままの状態になる人も少なくありません。
現代人は顎が小さくなってきているため、親知らずが正しく生えるスペースが足りず、トラブルを引き起こしやすいのが実情です。
親知らずと口臭の意外な関係性
親知らずと口臭は一見関係なさそうに見えますが、実は密接な関係があります。
以下のような理由から、親知らずが原因で口臭が悪化してしまうことがあるのです。
■ 磨き残しによる細菌の繁殖
親知らずは口の奥深くにあるため、歯ブラシが届きにくく、磨き残しが起きやすい部位です。
その結果、食べカスやプラーク(歯垢)がたまり、細菌が繁殖して悪臭の原因になります。
■ 歯ぐきの炎症(智歯周囲炎)
親知らずが中途半端に生えていたり、歯ぐきに覆われている場合、そこに細菌が入り込み炎症を起こすことがあります。
これを「智歯周囲炎(ちししゅういえん)」と呼び、腫れ・痛みだけでなく膿が出て悪臭を放つこともあります。
■ 歯と歯ぐきの隙間に汚れがたまる
横向きに生えていたり、隣の歯に食い込むように生えている親知らずは、歯と歯ぐきの間に深いポケットができます。
この部分に食べ物のカスや細菌が蓄積し、強いニオイを発生させる原因になります。
実際にあった「親知らずが原因の口臭」
例えば、ある30代男性は「どれだけ口臭ケアしてもニオイが消えない」と悩み、歯科を受診したところ、親知らずの奥で炎症が起きていると判明。
口の中では痛みもほとんどなく、自分では気づけなかったものの、レントゲンで炎症と膿の蓄積が確認され、抜歯後は口臭が劇的に改善したそうです。
このように、本人が自覚しづらくても、親知らずの影響で口臭が悪化しているケースは少なくありません。
親知らずによる口臭への対策
■ 歯科での定期的なチェック
親知らずは、問題がなくても一度歯科医に相談し、レントゲンで状態を確認してもらうのが理想的です。
見えない部分でトラブルが進行していることもあるため、早期発見が大切です。
■ 磨き方の見直しとフロス・歯間ブラシの活用
奥歯のケアにはテクニックが必要です。
親知らず周辺は特に磨きにくいため、小さめの歯ブラシやフロス、歯間ブラシを使って丁寧に清掃する習慣をつけましょう。
■ 抜歯を検討するケースも
親知らずが繰り返し炎症を起こしていたり、隣の歯や噛み合わせに悪影響を及ぼしている場合は、抜歯をすすめられることがあります。
不安がある場合は、セカンドオピニオンを受けてもよいでしょう。
まとめ:親知らずを放置しないことが、口臭予防にもつながる
親知らずは「生えているだけだから大丈夫」と思われがちですが、ケアが難しい場所だからこそ、口臭の原因になることが多い歯でもあります。
もし「最近口臭が気になるな…」と感じているなら、一度親知らずの状態をチェックしてみるのがおすすめです。
口臭の原因は意外なところに潜んでいるかもしれません。
歯科での定期チェックと日々の丁寧なケアで、口臭の悩みからも解放されましょう。
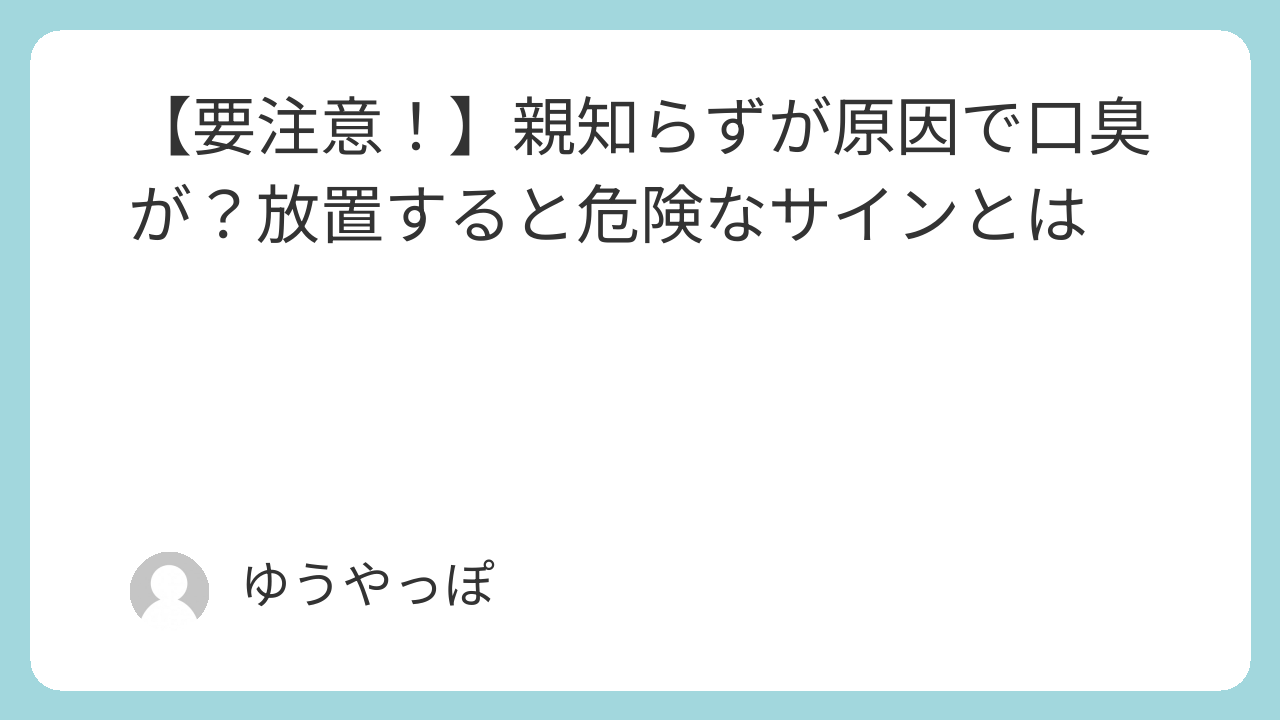
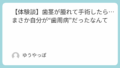
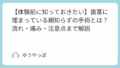
コメント