親知らず(第三大臼歯)は、通常10代後半から20代前半にかけて、最も奥に生えてくる永久歯です。この時期は「物事の分別がつく頃」という意味で「親知らず」と名付けられたと言われています。しかし、その生え方や存在意義は個人差が非常に大きく、完全に問題なく生えてくる人もいれば、深刻な口腔トラブルの原因となる人も少なくありません。多くの方が一度は「親知らず」という言葉を耳にし、その存在に悩まされた経験があるかもしれませんし、これからどうすべきか不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
現代人の顎は進化の過程で小さくなってきており、親知らずが生えてくる十分なスペースがないことが増えています。これが、親知らずが様々な問題を引き起こす最大の原因となっています。放置すると、単に親知らず自体の問題に留まらず、手前の健康な歯や歯茎、さらには全身の健康にまで悪影響を及ぼす可能性があります。
この記事では、親知らずの基本的な知識から、放置することのデメリット、一般的な抜歯の方法、特に「歯茎や骨に完全に埋まっている埋伏親知らず」の複雑な治療法、抜歯後の注意点、そして将来を見据えたケアに至るまで、親知らずに関するあらゆる疑問に、詳細かつ網羅的にお答えします。親知らずのことでお悩みの方、これから抜歯を検討している方が、安心して適切な選択ができるよう、専門的な知識に基づいた詳細な情報を提供し、皆様の不安を少しでも軽減することを目指します。
目次
1. 親知らずとは?その特異な性質とトラブルの根源
親知らずは、私たちの口の中に生える最後の永久歯です。通常、上下左右に1本ずつ、合計4本存在しますが、中には元々親知らずがない人(先天性欠如)や、2本や3本しか生えてこない人もいます。また、完全に骨の中に埋まったままで、一生顔を出さないことも珍しくありません。
親知らずがトラブルを起こしやすい主な理由を深掘りします。
- 顎の小型化と萌出スペースの不足: 人類の食生活の変化に伴い、顎の骨は徐々に小さくなってきました。これにより、親知らずが適切な位置に真っ直ぐ生え出るためのスペースが不足しがちです。結果として、親知らずは斜めに生えたり、手前の歯にぶつかって埋まったままになったり、一部だけ歯茎から顔を出したりといった「不適切な生え方」をすることが多くなります。
- 清掃の困難さ: 親知らずは最も奥に位置するため、通常の歯ブラシでは届きにくく、丁寧に磨くことが非常に困難です。特に、歯の一部だけが歯茎から出ている場合や、斜めに生えている場合は、歯と歯茎の間に深い溝やポケットができやすく、そこに食べかすやプラーク(歯垢)が溜まりやすくなります。これは、虫歯や歯周病の原因となる細菌の温床となります。
- 形態の異常: 他の歯と比べて、親知らずは根の形が複雑だったり、歯冠(歯の頭の部分)の形が不規則だったりすることがあります。これは抜歯を困難にする要因となるだけでなく、清掃性をさらに悪化させることにもつながります。
これらの特異な性質と環境要因が複雑に絡み合い、親知らずは口腔内における様々な問題の「震源地」となることが多いのです。
2. 親知らずを放置する深刻なデメリット・リスクの全貌
親知らずが問題なく真っ直ぐ生え、清潔に保たれている場合は抜歯の必要がないこともありますが、多くのケースでは放置することで以下のような深刻なデメリットやリスクが生じます。これらのリスクを理解することは、適切な対処法を選択する上で非常に重要です。
- 智歯周囲炎(ちししゅういえん)と重篤な感染症:
- 発生機序: 親知らずの一部だけが歯茎から顔を出している「半埋伏」の状態は、歯と歯茎の間にプラークや食べかすが溜まりやすく、細菌が非常に繁殖しやすい環境です。これにより、親知らずの周囲の歯茎に炎症が起こります。
- 症状: 初期には歯茎の腫れや軽い痛み、圧痛(押すと痛む)が見られますが、炎症が進行すると、激しい痛み、歯茎の真っ赤な腫れ、膿が出る、口が開きにくくなる(開口障害)、唾を飲み込む時に痛む(嚥下痛)、さらには発熱やリンパ節の腫れといった全身症状を伴うことがあります。
- 重篤なリスク: 炎症がさらに悪化すると、感染が周囲の組織や顎の骨、さらには喉の奥や顔の周りの軟部組織にまで広がり、「蜂窩織炎(ほうかしきえん)」と呼ばれる重篤な全身感染症を引き起こす可能性があります。これは命に関わることもある非常に危険な状態であり、緊急の処置(抗生物質の点滴、切開排膿など)が必要となります。
- 虫歯:親知らずと手前の歯を蝕む静かなる脅威:
- 発生機序: 親知らずは最も奥に位置し、その多くが斜めに生えていたり、一部が歯茎に覆われていたりするため、歯ブラシが届きにくく、徹底的な清掃が困難です。このため、親知らず自体が虫歯になるリスクが非常に高いです。
- 連鎖的な影響: さらに深刻なのは、親知らずと手前の健康な歯(第二大臼歯)との間にできた隙間に食べかすやプラークが慢性的に溜まることで、この手前の歯の奥側が虫歯になるリスクが飛躍的に高まることです。この部分の虫歯は発見が遅れやすく、進行しやすい上に、治療も非常に困難です。
- リスク: 親知らずの虫歯は治療が難しいことが多く、抜歯が選択される傾向にあります。そして、手前の歯が虫歯になった場合、その歯の治療も複雑になり、最悪の場合、健康な第二大臼歯まで抜歯しなければならなくなる可能性もあります。これは、噛む機能にとって大きな損失となります。
- 歯列不正(不正咬合)と審美性の低下:
- 発生機序: 顎のスペースが不足しているにもかかわらず、親知らずが無理に生え出ようとすると、手前の歯を押し出す強い力が加わります。
- 症状: この圧力によって、特に前歯の歯並びが乱れたり、元々歯並びが良かった人が、親知らずのせいで歯並びが悪化したりすることがあります。また、矯正治療後に親知らずが生えてくることで、せっかく整えた歯並びが後戻りしてしまう原因となることもあります。
- リスク: 歯並びの乱れは審美性の問題だけでなく、噛み合わせの悪化(不正咬合)にもつながり、食物を十分に咀嚼できなくなる、発音に影響が出る、清掃性がさらに悪化して他の歯の虫歯や歯周病のリスクを高める、といった機能的な問題を引き起こします。
- 歯根吸収(しこんきゅうしゅう):手前の歯を脅かす見えない危機:
- 発生機序: 親知らずが手前の歯の根(歯根)に直接ぶつかり、継続的な圧力が加わることで、手前の歯の根の表面が少しずつ溶けて失われていく現象を「歯根吸収」と呼びます。これは自覚症状がないまま進行することが多く、レントゲン検査で初めて発見されることがほとんどです。
- リスク: 歯根吸収が進行すると、手前の歯の安定性が損なわれ、グラグラと動揺したり、最悪の場合、健康な歯でありながら抜歯しなければならなくなる事態も起こりえます。これは、親知らずが原因で、本来残せるはずの重要な歯を失うという、非常に深刻な結果を招きます。
- 嚢胞(のうほう)形成と顎骨の破壊:
- 発生機序: 完全に歯茎や骨の中に埋まったままの親知らずの周囲の組織(歯胚や歯嚢と呼ばれる部分)から、液体が分泌されて袋状の良性腫瘍が形成されることがあります。これを「歯原性嚢胞」と呼びます。
- 症状: 嚢胞は通常、自覚症状がなく、歯科検診時のレントゲン検査で偶然発見されることが多いです。しかし、徐々に大きくなるにつれて、顎の骨を内部から溶かしたり、周囲の歯を圧迫したり、顔の形にわずかな変化をもたらしたりすることがあります。
- リスク: 嚢胞が大きくなると、顎の骨が薄くなり、外傷による骨折のリスクが高まります。また、稀に悪性化する可能性も指摘されており、発見された場合は早期の外科的処置(嚢胞の摘出と親知らずの抜歯)が必要です。
- 口臭の悪化:
- 発生機序: 親知らずの周囲に溜まった食べかすや、増殖した細菌は、硫化水素などの揮発性硫黄化合物を産生します。
- 症状: これらが不快な口臭の原因となります。特に、清掃が困難な半埋伏の親知らずや、智歯周囲炎を繰り返している場合は、口臭が慢性化しやすく、エチケットの面でも問題となります。
これらのデメリットを総合的に考慮すると、問題のある親知らずは、症状が出ていなくても早期に抜歯を検討することが、長期的な口腔健康維持のために強く推奨されます。
3. 親知らずの抜歯:種類と治療法の詳細
親知らずの抜歯は、その生え方(萌出度合いや方向)や根の形態、周囲の骨との位置関係によって、難易度が大きく異なります。歯科医師は、事前のレントゲンやCTなどの精密検査に基づいて、最適な抜歯方法を選択します。
3.1. 萌出している親知らずの抜歯(一般的な抜歯)
歯茎から完全に、または大部分が露出している親知らずの抜歯です。他の永久歯を抜くのと同様に、比較的簡単な処置で抜歯できることが多いです。
- 診査・診断: レントゲンで歯の根の形、骨の状態、周囲の組織との関係を確認します。
- 麻酔: 局所麻酔を十分に行います。表面麻酔を塗布後、細い針でゆっくりと麻酔液を注入することで、麻酔注射の痛みも最小限に抑えられます。麻酔が効くと、治療中の痛みはほとんど感じなくなります。
- 抜歯方法: 歯肉剥離(歯茎を少し剥がすこと)を必要としないことが多く、抜歯鉗子(ばっしけんし)と呼ばれる器具で歯をしっかりと掴み、適切な方向に力を加えながら抜きます。必要に応じて、ヘーベル(てこ)と呼ばれる器具で歯を少し揺らして抜きやすくすることもあります。
- 所要時間: 5~15分程度と比較的短時間で完了します。
- 術後の経過: 痛みや腫れは比較的軽度で、処方された鎮痛剤でコントロールできることがほとんどです。通常、数日から1週間程度で落ち着き、日常生活への影響も少ない傾向にあります。
3.2. 埋伏親知らずの抜歯(外科的抜歯)
歯茎や顎の骨の中に完全に、または大部分が埋まっている親知らずの抜歯です。特に、斜めや横向きに生えている(水平埋伏)場合は、難易度が高く、外科的な処置が必要になります。これは一般的な歯科医院でも行われますが、より専門的な技術と設備を要するため、口腔外科医が在籍する歯科医院や大学病院口腔外科などで実施されることが多いです。
- 診査・診断の徹底: 従来のレントゲンだけでなく、歯科用CT(コーンビームCT)を撮影し、親知らずの3次元的な位置関係、根の形態、顎の骨との関係、そして最も重要な「神経(下歯槽神経)や上顎洞との距離」を正確に把握します。これにより、手術のリスクを評価し、最適なアプローチを計画します。
- 麻酔: 通常は局所麻酔を十分に行いますが、患者さんの不安や恐怖心が強い場合、または非常に難易度の高いケースや複数の親知らずを一度に抜歯する場合は、静脈内鎮静法(点滴で鎮静剤を投与し、意識はありながらもウトウトとしたリラックス状態にする麻酔法)や、大学病院などでは全身麻酔が選択されることもあります。これにより、患者さんは痛みや恐怖を感じることなく、安全に手術を受けることができます。
- 抜歯の具体的な手順:
- 切開・剥離: 歯茎(歯肉)をメスで慎重に切開し、親知らずとその周囲の骨が見えるように剥離します。
- 骨の削除(骨削合): 親知らずが顎の骨の中に埋まっている場合は、タービン(高速で骨を削る機器)やピエゾサージェリー(超音波骨削合装置)を用いて、親知らずを覆っている骨を少量ずつ慎重に削除します。この際、周囲の健康な組織へのダメージを最小限に抑えるよう、冷却水をかけながら行います。
- 歯の分割: 親知らずが大きかったり、複雑な形態をしていたり、あるいは骨の削除量を最小限に抑えるために、タービンを用いて親知らずをいくつかの部分(通常は2~3分割)に慎重に分割します。これにより、小さなピースにして取り出すことで、周囲の骨や組織への負担を最小限に抑えることができます。
- 抜歯: 分割した歯片を、ヘーベルや鉗子を用いて一つずつ慎重に取り除きます。
- 清掃・止血・縫合: 抜歯窩(歯を抜いた後の穴)の内部を洗浄し、残った骨片や感染源がないか徹底的に確認します。止血処置を行った後、剥離した歯茎を元に戻し、糸でしっかりと縫合します。縫合することで、抜歯窩の保護、止血、感染予防、そして治癒の促進を図ります。
- 所要時間: 難易度によって大きく異なり、30分~1時間以上かかることもあります。特に水平埋伏や完全埋伏の場合は、1時間以上を要することも珍しくありません。
- 術後の経過: 萌出している親知らずの抜歯に比べて、痛みや腫れが強く出やすい傾向があります。これは、骨を削ったり歯茎を切開したりするため、組織への侵襲が大きいからです。通常は術後2~3日で腫れがピークを迎え、その後徐々に引き、1週間~10日程度で落ち着いてきます。顔の皮膚に内出血が生じて黄色っぽくなることもありますが、これも時間の経過とともに消失します。処方された鎮痛剤や抗生物質を指示通りに服用することが、痛みのコントロールと感染予防に不可欠です。縫合した場合は、1週間~2週間後に抜糸が必要です。
4. 埋伏親知らずの抜歯における特に重要な注意点とリスク
「歯茎に埋めこんじゃってる親知らず」は、多くの人が抜歯に不安を感じる対象であり、特に注意すべきリスクがいくつか存在します。これらのリスクを事前に理解し、歯科医師と十分に相談することが、安全な治療のために不可欠です。
- 下歯槽神経損傷による神経麻痺のリスク:
- メカニズム: 下顎の親知らずの根の近くには、下唇、顎の皮膚、歯茎の感覚を司る「下歯槽神経」が走っています。親知らずの根がこの神経に非常に近い、あるいは接触していることがあります。抜歯の際に、根尖が神経を圧迫したり、歯を抜く際の器具操作によって神経が損傷を受けたりすると、神経麻痺が生じる可能性があります。
- 症状: 下唇、顎の皮膚、歯茎などに「しびれ」や「感覚鈍麻(感覚が鈍くなる)」が生じます。多くの場合、一時的なもので数週間から数ヶ月で回復しますが、稀に永久的にしびれが残ることもあります。
- 対策: 抜歯前に歯科用CTを撮影し、親知らずの根と下歯槽神経の位置関係を正確に把握することで、リスクの高いケースを特定し、慎重な手術計画を立てることが非常に重要です。術中も細心の注意を払い、神経への影響を最小限に抑える技術が求められます。
- 出血のリスク:
- メカニズム: 抜歯中は麻酔薬に含まれる血管収縮剤で出血を抑えますが、術後に麻酔が切れると、抜歯窩からじわじわと出血が続くことがあります。
- 対策: 抜歯後は清潔なガーゼをしっかりと噛んで圧迫止血することが重要です。また、血行を促進するような行為(激しい運動、飲酒、長時間の入浴など)を避ける必要があります。出血が止まらない場合は、すぐに歯科医院に連絡しましょう。
- ドライソケット(Alveolar Osteitis):
- メカニズム: 抜歯窩(歯を抜いた後の穴)には、通常、血餅(けっぺい:血の塊)が形成され、これが骨や歯茎の再生の足がかりとなります。しかし、過度なうがいや喫煙、細菌感染などによってこの血餅がうまく形成されなかったり、剥がれてしまったりすると、骨が露出した状態になり、強い痛みを伴います。
- 症状: 抜歯後2~4日後に、突然、薬が効かないほどの激しい痛みが起こります。口臭を伴うこともあります。
- 対策: 抜歯後は、歯科医師の指示に従い、過度なうがいを避けましょう。喫煙はドライソケットのリスクを大幅に高めるため、抜歯後少なくとも1週間は禁煙することが強く推奨されます。ドライソケットになった場合は、抜歯窩の清掃と薬剤の塗布などの処置が必要です。
- 顎骨骨折のリスク:
- メカニズム: 非常に稀な合併症ですが、特に高齢者や骨粗しょう症の患者さん、あるいは非常に深く大きく埋伏している親知らずを抜歯する際など、顎の骨が脆弱になっている場合に、抜歯の強い力によって顎の骨が折れてしまう(顎骨骨折)ことがあります。
- 対策: 事前のCT診断と慎重な手術計画、そして経験豊富な術者による繊細な手技が求められます。
- 上顎洞との交通:
- メカニズム: 上顎の親知らずの根が、上顎洞(じょうがくどう:鼻の横にある空洞)に非常に近い位置にある場合、抜歯によって上顎洞と口腔が交通してしまうことがあります。
- 症状: 交通孔ができた場合、鼻から空気が漏れるような感覚や、鼻腔に液体が逆流するような症状が出ることがあります。
- 対策: 交通孔が小さい場合は、抜歯窩を丁寧に縫合することで自然治癒を期待できますが、大きい場合は専門的な処置が必要になることもあります。抜歯前にCTで上顎洞との距離を確認し、リスクを評価することが重要です。
これらのリスクは、適切な診断と計画、そして経験豊富な歯科医師による丁寧な手術によって最小限に抑えることができます。患者さん自身も、歯科医師からの説明をよく聞き、不安な点は遠慮なく質問し、術後の注意点を守ることが大切です。
5. 親知らず抜歯後の過ごし方と注意点:早期回復のために
抜歯後の適切なケアは、合併症を防ぎ、早期回復を促すために非常に重要です。歯科医師やスタッフから受けた指示を忠実に守りましょう。
- 止血の徹底: 抜歯後、歯科医師から渡されたガーゼや綿を、抜歯窩に当てて30分~1時間程度しっかりと噛み続けましょう。これにより、血餅の形成を促し、止血を助けます。唾液に血が混じる程度であれば問題ありませんが、多量の出血が続く場合は、再度清潔なガーゼを噛むか、歯科医院に連絡してください。
- うがいは控えめに: 抜歯当日は、頻繁なうがいや強くうがいをすることは避けましょう。血餅が剥がれてしまい、ドライソケットの原因となる可能性があります。翌日以降も、強くブクブクうがいをするのではなく、軽く口をゆすぐ程度に留めましょう。
- 安静を保つ: 抜歯当日は、激しい運動、長時間の入浴やシャワー(短時間のシャワーは可)、飲酒、喫煙を控えましょう。これらは血行を促進し、出血や腫れを悪化させる原因となります。特に喫煙は治癒を遅らせ、ドライソケットのリスクを大幅に高めます。
- 食事の注意: 麻酔が完全に切れてから食事を摂りましょう。麻酔が効いていると、頬や唇を噛んでしまう可能性があります。抜歯当日は、やわらかく、刺激の少ない(熱すぎる、冷たすぎる、辛すぎるものは避ける)食事を、抜歯した側ではない方でゆっくりと噛むようにしましょう。ストローの使用も、口腔内の圧力を変化させ、血餅が剥がれるリスクがあるため、避けるのが賢明です。
- 薬剤の服用: 処方された痛み止め(鎮痛剤)と抗生物質は、歯科医師の指示通りに服用しましょう。痛み止めは、痛みが始まる前に飲むと効果的です。抗生物質は、感染予防のために指示された期間、全て飲み切ることが重要です。
- 冷却: 腫れを軽減するために、抜歯した頬の外側を、濡れタオルや冷却パックを当てて冷やすと良いでしょう(ただし、冷やしすぎると血行不良を招くため、適度に)。腫れのピークは術後2~3日後が一般的です。
- 患部に触らない: 舌や指で抜歯窩を触ったり、つついたりすることは絶対に避けましょう。細菌感染や血餅の剥離の原因となります。
- 口腔ケア: 抜歯した部分を避けて、他の歯は普段通り丁寧に歯磨きしましょう。口腔内を清潔に保つことは、感染予防につながります。
通常、抜歯後の痛みや腫れは数日でピークを迎え、1週間~10日程度で徐々に落ち着いてきます。縫合した場合は、1週間~2週間後に抜糸が必要です。抜糸時に、抜歯窩の治癒状態を確認し、問題がなければこれで治療は一段落となります。
6. 親知らずの抜歯を検討する最適なタイミング
親知らずの抜歯の必要性やタイミングは、個々の親知らずの状態、患者さんの全身の健康状態、ライフスタイルによって異なります。歯科医師と十分に相談し、納得した上で治療方針を決定することが重要です。
- 繰り返される痛みや腫れ、炎症: これが最も一般的な抜歯の理由です。智歯周囲炎を繰り返している場合や、炎症が重篤化するリスクが高い場合は、抜歯を強く推奨されます。
- 親知らず自体や手前の歯に虫歯がある場合: 親知らずや手前の歯が虫歯になっており、清掃が困難で治療も難しい場合は、抜歯が最善の選択肢となります。
- 歯周病への影響: 親知らずの周囲の歯茎が慢性的に腫れていたり、深い歯周ポケットが形成されていたりする場合、手前の歯の歯周病を悪化させる原因となるため、抜歯が推奨されます。
- 歯列矯正を計画している場合: 親知らずが歯並びに悪影響を及ぼす可能性(前歯の叢生など)があるため、矯正治療を開始する前に抜歯することが一般的です。また、矯正治療後の後戻りを防ぐためにも、抜歯が検討されます。
- 嚢胞や腫瘍などの病変が確認された場合: 親知らずの周囲に嚢胞や腫瘍といった病変がレントゲンやCTで確認された場合は、放置すると顎の骨を溶かす可能性があるため、早期の抜歯と病変の摘出が必要です。
- 将来的なリスクが高いと診断された場合: 現在は自覚症状がなくても、レントゲンやCTで確認できる異常(神経との近接、深い水平埋伏など)があり、将来的にトラブルを引き起こす可能性が非常に高いと診断された場合は、症状が出る前の抜歯を勧められることがあります。特に、若い時期(10代後半~20代前半)の方が、骨がやわらかく治癒能力も高いため、抜歯が比較的容易で術後の回復も早い傾向があります。また、高齢になってからの抜歯は、骨が硬くなっていることや、全身疾患のリスクが高まることから、抜歯の難易度が上がり、合併症のリスクも高まる可能性があります。
7. 親知らず抜歯後の代替治療と口腔機能の維持
親知らずの抜歯は、多くの人にとって一時的な不快感を伴うかもしれませんが、それは長期的な口腔内の健康と快適な生活を守るための大切なステップです。抜歯後、特に複数の親知らずを抜いた場合や、親知らずが歯列弓の重要な一部として機能していた場合には、口腔機能の維持を考慮する必要があります。
- 噛み合わせの調整: 親知らずが抜かれたことで、噛み合わせのバランスが変化することがあります。抜歯後、必要に応じて残っている歯の噛み合わせの微調整が行われることがあります。
- 隣接する歯のケア: 親知らずが抜かれた後のスペースは、しばらくの間、食べ物が詰まりやすくなることがあります。隣接する歯の虫歯や歯周病を予防するために、より丁寧な口腔ケアと定期的な歯科検診が重要です。
- 失われた歯の代替: ごく稀に、親知らずが唯一の奥歯として機能していた場合や、他の奥歯も失われている場合には、抜歯後にインプラントやブリッジなどの補綴治療が検討されることもあります。しかし、ほとんどの親知らずは機能的に重要ではないため、抜歯後のスペースに特別な処置は必要ありません。
- 抜歯窩の治癒促進: 抜歯窩の骨の再生を促すために、特定の症例では、人工骨補填材などが使用されることもあります。これにより、骨の回復を早め、将来的な顎骨の吸収を抑制する効果が期待できます。
8. まとめ:親知らずと上手に付き合い、健康な未来へ
親知らずは、私たちにとって時に悩みの種となる存在ですが、その特性とリスクを正しく理解することで、適切な対処が可能になります。放置することによるデメリットは非常に大きく、単に親知らずの問題に留まらず、手前の健康な歯を巻き込み、さらには全身の健康にまで悪影響を及ぼす可能性があります。
「親知らずの抜歯は怖い」と感じるかもしれませんが、現代の歯科医療は目覚ましい進歩を遂げています。局所麻酔はもちろんのこと、静脈内鎮静法などの技術、歯科用CTやマイクロスコープといった精密な診断・治療機器の活用、そして何よりも経験豊富な歯科医師の存在により、多くの場合、安全かつ快適に治療を受けることができます。特に、歯茎や骨の中に埋まっている埋伏親知らずの抜歯は、専門的な知識と高度な技術を要するため、信頼できる口腔外科医や、口腔外科を標榜する歯科医院での相談・治療が推奨されます。
親知らずの抜歯は、一時的な不快感や負担を伴うかもしれませんが、それは将来の口腔内の健康と快適な生活を守るための大切なステップです。親知らずに関する痛み、腫れ、違和感、あるいは歯科検診で指摘された場合は、決して自己判断で放置せず、早めに歯科医院を受診し、専門家のアドバイスを求めましょう。適切な時期に適切な治療を受けることが、健康な口腔環境を維持し、豊かな人生を送るための賢明な選択となります。


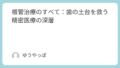
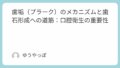
コメント